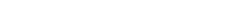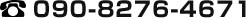函館送迎観光貸切タクシー・ジャンボタクシーでの『函館山』観光案内です。


函館山
函館山は、標高335mの御殿山を中心に、薬師、観音、愛宕、七面、地蔵、鞍掛と、7つの山からなっている自然公園で、この山を遠くからながめますと、ちょうど牛が臥せているように見える所から臥牛山とも呼ばれております。
また、自然に生える杉は、青森県が北限となっておりますが、この函館山の杉は、今から180年程前に植林されたものです。
函館山から見る函館市街地は、右が津軽海峡、左は函館港です。
函館港はその形が巴のようになっていますので、巴港とも呼ばれています。
今から140年程前の安政2年(1855年)、伊豆の下田と並んで、外国船に薪や水・食料を補給する港として、さらに、安政6年には、長崎・横浜とともに貿易港として開かれた港です。


また、函館港でクレーンが見えるところは、函館ドックです。
港の向こうに沢山の石油タンク並んでいる辺りは七重浜といいます。
昭和29年9月、北海道を襲った15号台風によって、青函連絡船の洞爺丸を始め、4隻の船があの七重浜の沖合で、次々と転覆、1500余名の尊い命が奪われています。
続いて遠くに見える高い煙突は、日本セメント上磯工場です。
海に突き出ている防波堤のようなものは、セメントをタンカーに送り込む桟橋です。

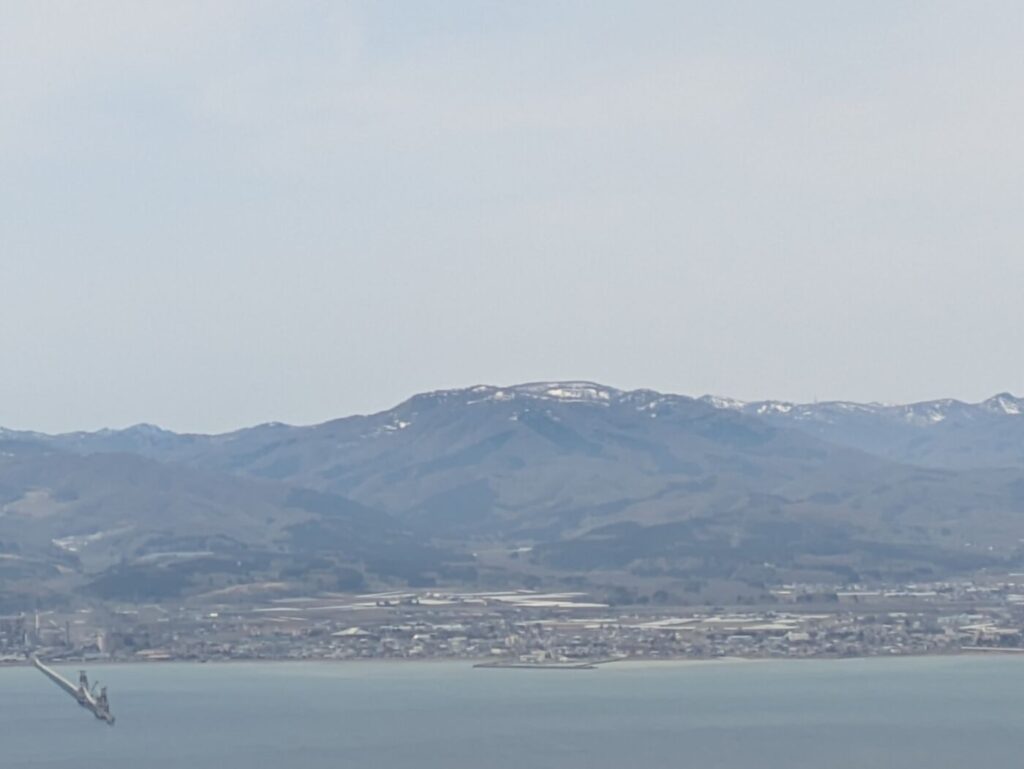
矢越岬
矢越岬のかげに、青函海底トンネルの出入り口があります。
青函海底トンネルは北海道の白神岬と、本州側の、青森県龍飛岬を結んでいるもので、海底部分が23.3㎞、陸上のトンネルも含めると、全長53.85㎞という世界一長いトンネルです。
(英仏海峡のユーロトンネルは50.5㎞)
函館山展望台には、ブラキストンラインの記念碑と、伊能忠敬のレリーフが建てられております。
トーマス・ライト・ブラキストン
ブラキストンは、函館に20年間暮らした、イギリスの貿易商ですが、鳥や動物にも関心が深く、いろいろと調べているうちに、北海道の動物(ヒグマ・オオカミ・シマリス等)がシベリア系なのに対して、本州にすむ動物(サル・イノシシ・カモシカ)は満州や、中央アジア系で、その分かれ目が、津軽海峡であるということを発見しました。
このため、動物学上では、津軽海峡をブラキストン・ラインと呼んで、その功績を讃えております。
伊能忠敬
また、伊能忠敬は江戸時代の測量家で、日本ではじめて、正確な日本地図を作った人です。
50才から天文学を学び蝦夷地にやって来たのは56才のとき、5人の助手とともに、この函館山に登り、測量の起点を定めました。
そして、根室に近い、西別までの海岸線820㎞を歩き、その歩数で距離を測ったそうです。
また、忠敬の日本地図が完成したのは、文政4年(1821年)、忠敬の死後3年のことですが、測量できなかった北海道の西海岸は、弟子の間宮林蔵の手で書きたされています。
また、函館山には、あちこちに要塞の跡が見えますが、函館山は、明治32年から終戦までの50年間、津軽海峡を守る、軍の要塞となっていたところです。
この函館山は大昔、火山の爆発によって生まれたといわれ、海中の島でしたが、長い間に、海流の運んだ砂がたまり、陸地とつながったものです。


函館山夜景
函館家の夜景は長崎・神戸と並んで、日本3大夜景の1つにあげられています。
街の灯りが、宝石をちりばめたように輝き、暗い海には、イカ釣り船の漁火が点々と続く様は、まさに『100ドルの夜景』です。
函館市の観光対象で全国的にも有名なのが、函館山(標高335m)から望む函館市街地の景観で、特に夜景は魅力的です。
第二次世界大戦後、要塞として閉ざされていた函館山が解放され、自動車道路やロープウェイの整備が進みました。
夏季の観光シーズンには道路の渋滞が激しくなり、夜の一定時間におけるマイカー規制が行われるようになりました。
函館市内の観光対象は、函館山と西部地区から函館駅周辺地区、五稜郭地区、湯の川温泉・トラピスチヌ修道院地区という3地区に分布しております。
良好な自然環境が保全されてきた函館山の山麓一帯は、函館観光の中心とも言える地区で、国の重要文化財でもある函館ハリストス正教会を始めとした数多くの教会や寺院、外国人墓地、旧函館区公会堂を始めとした多くの洋式建造物、函館港臨海地区の金森倉庫のような赤レンガ造りの倉庫群など、明治から昭和初期にかけての歴史的建造物が点在しており、異国情緒あふれる空間を形成しております。
こうしたことから、1989年(平成元年)「函館市元町末広町伝統的建造物群保存地区」が指定されました。
西部地区の景観を特徴づけているのは、こうした歴史的建造物だけではありません。
函館山山麓から港に向かって「二十間坂」や「基坂」を始め多くの坂があり、ここからの眺めが独特の景観を生み出しているとも言えます。
路面電車の系統が分岐する十字街電停付近は、かつて函館市の中心商業地域であった場所であり、かつての賑わいを物語る歴史的な建物が今でも残っています。
このうち、丸井今井百貨店として1923年建築された建物を活用して、2007年に函館市地域交流まちづくりセンターがオープンしました。
1階の広々とした空間には喫茶や情報コーナーがあり、市民活動の拠点としてだけではなく、観光情報センターとしても機能しております。
函館駅周辺は、2003年(平成15年)に新しくなった函館駅を中心に、隣接する函館朝市には約300の店がひしめきあい、多くの観光客が訪れております。
津軽海峡
『しょっぱい川』という川をご存知でしょうか?「塩からい川」・・・つまり津軽海峡のことで、北海道に住む、ご年配の方たちが使っていた言葉です。
本州から移住した方たちの、故郷を懐かしむ心が、このような言葉を生み出したものと思います。
確かに、太平洋と日本海から入る潮の流れは、「川」と呼んでおかしくないほどに流れが速く(1時間に11㎞の速度)、昔は渡るのに大変な苦労をしたそうです。
松前のお殿様が、江戸へ行く時には、津軽海峡を渡って、青森県の三厩に着くと、合図のノロシで城中に知らせ、藩士一同、登城して、お殿様の無事を祝ったということです。
石川啄木が、島崎藤村が、そして、三木露風が詩い、さまざまな人生を乗せた連絡船が行き交ったこの海峡も、今では、世界一長い海底トンネルがつくられ、貨物列車や新幹線が、本州と北海道をつないでおります。


函館市の歴史
函館の「函」の字は、明治になってから改められたもので、それまでは箱根の「箱」という字を使っておりました。
今から550年ほど前、このあたりの豪族だった河野政通が、函館山の麓に館を築いたとき、その館が、箱のような形に見えたところから、「箱の館」箱館と呼ぶようになったといわれています。
江戸時代には現在の松前、当時は福山といっていましたが、この福山に本拠を構えていた、松前藩の番所となり、江差や福山とならぶ「松前三湊」の1つとして栄えました。
江戸時代も後半、幕府が松前藩にかわって、直接蝦夷地をおさめることになり、この函館に奉行所を設けました。
千島列島ぞいに、ロシアの勢力が南下しはじめ、いろいろな事件が起こるようになったからからです。
伊能忠敬が蝦夷地を測量したり、高田屋嘉兵が、択捉島への航路を開くなど活躍をしたのは、ちょうどこのころです。
こうして、蝦夷地の中心となった函館は、急速な発展を遂げ、安政2年(1855年)に、外国船が使う薪や水、食糧などの供給地として港を開き、続いて、4年後の安政6年には、長崎・横浜とともに、日本初の貿易港となってからは、外国船の往来がはげしくなり、領事館も置かれて、多くの西洋文化が流れ込みました。
函館奉行も、積極的にこれを取り入れて、諸術調所という、研究教育施設をつくって、新しい知識を勉強しようとする、若者達の要求に答え、医学所をつくり、中川五郎治に、日本で初めての種痘を行わせたりしています。
やがて明治維新をむかえ、新政府は、函館奉行の仕事を受け継いで、北海道開拓の計画を進めました。
しかし、このとき、榎本武揚の率いる幕府脱走軍が五稜郭を襲い、箱館戦争がおこります。
明治元年から明治2年かけてのことでした。
その後、政治の中心は札幌に移ってしまいましたが、北海道の海の玄関口として、重要性は変わることなく、今日まで発展を続けてきました。