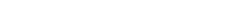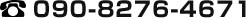北海道観光個人タクシー高橋の上富良野町・JALのCMで登場した『嵐の木』と美瑛の丘・木です。
上富良野町に有る、JALのCMで登場した、5本の松の木が「嵐の木」です。
上富良野町
上富良野町は、大正15年、十勝岳の爆発で144名の尊い生命と多くの田畑をうしない、一時は村を丸ごと放棄しようという説と、どうしても、もと通りにという復興説が出て、議論されました。
それが今ではビールの原料ホップ、香水の原料ラベンダー、そのほか、アスパラガス、ビートなど、北海道の特産物を生産する農村となり、噴煙たなびく十勝岳は、まちの重要な観光資源になっています。
美瑛町、クリスマスツリーの木です。

美瑛町
美瑛町は、十勝岳のふもと、上川盆地の南のはしにひらけた田園地帯で、美瑛町の特産物は、麦・ジャガイモ・豆・ビートなどの畑作が中心です。
なだらかな美瑛の丘に畑作の緑、美瑛ラベンダーの紫、ピンクのコスモスなどが、まるでジュータンを敷きつめたように、美しい丘の町美瑛の農村景観をつくっています。
美瑛町「展望花畑四季彩の丘」は、展望が素晴らしい丘の町美瑛に15haもの広さを有しています。
春から秋までのお花の季節には、数十種類の草花が咲き乱れる、花の楽園です。又写真ギャラリー「拓真館」など、美瑛の美しさを満喫したい人がおとずれています。
ここは、明治27年、兵庫県の小林直三郎という人が、同志とともに入植したのがきっかけとなり、その後、いくつもの農場が作られて開拓が進みました。
そして戦後には、旭川の第七師団演習場(6600ha)や、御料地(皇室の所有地、2900ha)など、広大な国有地でしたが、戦争で被害をうけた人達や、ひきあげてきた人達に解放されたものです。
美瑛の地名のおこりは、アイヌ語の「ピイェ」から来ています。
「ピイェ」とは、「油ぎった」という意味で、美瑛川が十勝岳から流れ出る硫黄分のために、白く濁っていたことから、こように呼ばれたものです。

マイルドセブンのCMで登場した、マイルドセブンの丘です。



マイルドセブンの丘
マイルドセブンの丘、丘の上にカラマツの防風林があり、昭和52年にタバコマイルドセブンのパッケージに使われたことで、いつしか観光スポットになりました。
この他にいろいろな観光スポットがありますが、それらの多くは、ここを訪ねた旅人や、写真家によって命名されたそうです。


親子の木です。

親子の木
丘の上に3本の木が立っています。その木をさいて「親子の木」と申します。
木の種類は「かしわ」です。
風雪に耐えながら丘の上に立つ真中の小さな木を、両サイドの大きな木が、まるで子供を守る両親のように見える事から、誰云うとmpなく「親子の木」と名付けられました。


セブンスターのCMで登場した、セブンスターの木です。

セブンスターの木
木の種類は柏で、昭和51年に観光タバコ「セブンスター」のパッケージに掲載された事から、町役場には問合せが多くなり、自然的に町は「セブンスターの木」と命名する事になりました。
また、時を同じくして、ラベンダーの花畑が国鉄のカレンダーに掲載され、まるで申し合わせたように美瑛、富良野に本州方面からの旅好き、写真好き、花好き、物好き(ごめんなさい)が、少しづつ訪ねて来るようになりました。
単なる農業の町であったこの美瑛町を大きく変えた功労の木ですが、しかし、果たしてセブンスターの木そのものは、大勢のお客様の御来木を喜んでいるかどうかは定かではありません。
余りの車両の多さに農道は舗装され、駐車場まで用意される始末です。この駐車場の一角に歌人・小林孝虎の詠んだ歌碑が建っています。
十勝嶺ねの はるかに見ゆる 丘のうえ
郭公のこえとほくなりゆく
小林孝虎氏は旭川在住、日本歌人クラブ委員、北海道歌人会委員で、大正12年、深川市に生を受け、室蘭、旭川、富良野で教員を勤め、昭和59年退職、在職中から歌を詠み、歌人として活躍している。
この歌碑は平成9年5月、美瑛町、北方短歌社の支援によって建立されました。

セブンスターの木の横の白樺並木です。
白樺
歌人若山牧水は『渓あいの 路はかなしく白樺の
白き木立に きわまりにけり』と歌っておりますが、本州では山岳地帯か高原でなければ見られない白樺も、北海道ではいたるところで見られます。
イギリスではこの木を、白いドレスをまとった貴婦人に見立てて「森のレディ」と呼んでいるそうで、とくに、緑につつまれた森や高原の中では、白さが一層きわ立ち、明るく清楚な雰囲気をただよわせ、レディの呼び名にふさわしい風情を見せています。
ところが、このようなロマンチックな白樺も、むかしは、農家の人達に「なーんだ、ガンビか!」といわれて人気がありませんでした。
それは、白樺はやせ地のシンボルで、白樺の生える土地には、何を植えても駄目だったからです。
そのうえ、腐りやすく、牧場の柵にしても、2年ともたず、薪ににしても火持ちが悪く、せいぜい白い皮だけが「ガンビ」と呼ばれて、焚き付けに使われる程度だったのです。
しかし、その白樺も、最近ではフローリングやパルプ材として、大いに利用されるようになりました。

日産ケンとメリーのスカイラインのCMで登場した、ケンとメリーのポプラの木です。

ケントメリーの木
昭和47年に日産自動車のCMで「愛のスカイライン~」を歌ったケンとメリーの名前をとって「ケンとメリーの木」と町役場が名付けました。
地元では「ケンメリの木」と略して呼んでいます。
(大久保さんのお店の庭に、当時の車「スカイラインケンメリ」が置いてあります。ここのバター付きのゆでジャガイモ、美味しいですよ!!)
この木はポプラの木で、この辺りの土地の所有者・大久保さんのおじいちゃんが、大正12年、隣りの農場との境界として植えたのだそうです。
ポプラはもともと北海道の木ではありませんので、四国徳島から北海道に開墾に入った大久保さんには大変珍しい木だったようです。
成長して現在のケンとメリーの木になりました。
大久保のおじいちゃんも草場の陰で、「わしの植えた木がここまで有名になるとは、わしも鼻高々じゃ!」なんて言っているのでは?
現在、農地を30ha所有しており、ペンション・ケンとメリーと売店の経営もしております。


ケンとメリーの木の近くの、ポプラ並木です。
ポプラ
ポプラ並木です。
ポプラは正しくは、クロポプラといい、原産地のヨーロッパからアメリカに渡り、明治の中頃、日本に入ってきました。
背の高い木で、ところによっては、40mにもなるものもあるそうです。
ポプラは、ギリシャ神話にいくか登場して参ります。
では、ポプラの枝がなぜ天に向かって伸びているか・・・そのお話をご紹介致しましょう。
むかし、むかし、ぽぷらの枝が、横に伸びていたころのお話です。
森の木々が眠りについた夜ふけ、一人の老人が、ポプラの枝にソーッと、丸くて重い物を隠して行きました。
それは、女神のアイリスが大切にしていた金のツボでした。
翌朝、神殿では上を下への大騒ぎ、なくなった金のツボを、手をつくして捜しまわり、森の木たちにも聞いて見ましたが、だれもツボのありかを知りません。
そこで、天空の神ゼウスが、すべての木にむかって、「枝を高く上げろ」と命じました。
何も知らないポプラも、みんなと一緒に枝をさしあげました。
するとどうでしょう、あれほど捜していた金のツボが、ころがり落ちてきたのです。
それからというもの、ポプラはいつも枝を天に向けて、疑われないようにしているということです。
ところで、クロポプラには、オスの木とメスの木があり、メスの木の大部分は、枝を横に広げています。
ですから、草ぼうきを立てたような姿のポプラは、オスの木と考えてもよさそうです。
ポプラは、さし木などで、簡単に増やすことができ、しかも成長が早いので、いろいろな品種改良が行われております。
神話に出て来るほどの古い木ですが、次から次へと改良され、新しい品種が生まれて、放っておくと混乱をきたすありさまです。
そのため、国際ぽぷら委員会という組織がつくられていて、ここで、新しい品種と認めなければ、ポプラの仲間には、入れないようになっています。
日本で見られる代表的な品種は、イタリアポプラ・セイヨウハコヤナギなどと呼ばれる改良ポプラです。
1年に3mも伸びることもあり、15年位で、立派な樹木に成長します。あまり役に立たないクロポプラとちがい、合板やパルプ材として、またマッチの軸などにも利用されています。