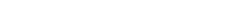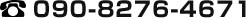小樽観光TAXI 旧手宮線・遊歩道を散歩しました。
旧手宮線・遊歩道を散歩しました。
旧手宮線は、小樽や北海道の発展に大きく関わっています。
明治13年に北海道開拓の為の重要事業の一つとして、「幌内鉄道」小樽・手宮~札幌間が日本で3番目、北海道で最初に開通しました。
幌内鉄道は、開拓物資等を小樽から札幌までの区間で輸送し、明治15年には幌内炭鉱が有る、三笠幌内まで、全面開通して石炭輸送が本格的に始まりました。
その後石炭の供給を続け、日本の発展に貢献しています。石炭輸送だけでなく、飼料やセメント、小麦粉等も輸送しておりましたが、トラック輸送などの普及により、昭和60年11月5日、105年と言う鉄道歴史の幕を閉じました。
北海道の鉄道
明治13年(1880年)1月に若竹第三トンネルの工事から開始された後、工事は水天宮第一トンネル(現存せず:花園橋付近)、住吉第二トンネル(現存せず:南小樽駅付近)、熊碓第四トンネル(現存:車馬車のものを改良)と小樽市内の4ヶ所のトンネルを次々と開削していきました。
また、この区間の最大の工事と見られていた入船川の谷をまたぐ陸橋も着工するなど順調に工事は進んでいきました。
この間の9月28日にはクロフォードが買い付けた鉄道資材をつんだトベイ号が手宮桟橋に着岸します。
「義経」などの機関車は早速手宮桟橋の付け根の作業場で組み立てが開始され、同時にレールの敷設もはじまりました。
そして、10月24日、手宮から熊碓までの敷設が完成し、試運転が行われました。
幌内鉄道の写真としては一番有名な、入船陸橋渡る弁慶号のシーンが撮影されたのがこの日です。
ちなみに義経号はまだ組み立て中(完成は12月)で動く事ができる蒸気機関車は弁慶号のみでした。
熊碓から銭函までの区間はすでに馬車道としてクロフォードが建設していたため順調に工事は進みます。
ちなみにこの区間には現存する北海道最古のトンネル通称「義経トンネル」(当時は張碓第五トンネル)と最古のレンガ橋脚「張碓鉄橋」が残っています。
熊碓までの試運転からわずか18日後、の11月11日手宮・銭函間の「仮運転」が行われます。
この段階ですでに営業を行っていたと推測され、北海道初めての鉄道は実質的にこの日から運行(機関車は弁慶号のみ)されていたといえます。
一週間後には軽川(手稲)まで延長し、二日後の11月20日、手宮~札幌間、35.9㎞が開通し、28日に運転式が行われます。
線路工事はもちろんトンネル工事、橋梁工事などすべての工事着工から完成までわずか11ヶ月というきわめて促成の工事でした。もっともそれに効果があったといわれるのは、レールの細さでした。
明治5年(1872年)、日本で最初に鉄道が敷かれた新橋~横浜間で使用されたレールはイギリス、ダーリントン社製の60ポンド(27.216kg)レール(双頭型)でしたが、手宮~札幌間で使用されたものは30ポンド(13.608kg)のレール(T字型)で半分しかないものでした。
耐久度や加重能力はかなり劣るもでしたが、施工が容易であり、クロフォードが活躍したアメリカ西部でも用いられた方法でした。
開通から全通
幌内までの全通
順調に開通した手宮~札幌間にくらべ札幌~幌内間は開拓の手があまり入っていないことと地形的な困難さもあり、松本たち残された日本人技師たちは苦労を重ねることとなります。
明治13年(1880年)中に創成川から豊平川までの間の基礎工事を終わり、本格的な施工は雪解けを待って翌年明治14年(18881年)6月から着工されました。
もっとも困難であったのは山間部の幌内ではなく、札幌近郊の豊平川から江別にかけてでした。
当時の厚別は泥炭地が広がっていたからですが、それ以上に技術者たちを悩ませたのは豊平川の氾濫でした。
ここにはトラスト式鉄橋を架けたのですが、工事完了をまたずに流されてしまい、結局全通時には仮橋のまま、という状態でした。
そのような難工事を抱えながらも、札幌まで開通したのは1年半後の明治15年(1882年)6月25日は江別までの仮営業が開始されました。
そして5ヵ月後、明治15年11月13日、手宮~幌内間91.2㎞が全通し、同時に営業運転が開始され、14日には幌内鉄道本来の目的である石炭の搬出の第一号貨車も出発しました。
翌年明治16年(1883年)2月2日に太政官第三号不達によって正式開業となります。
そして明治16年9月17日に、幌内鉄道開業式が開催されています。
「幌内鉄道開通」はこの3つの段階があるのですが、明治15年(1882年)中は豊平川だけではなく、幾春別川や幌向川の橋も破損するなど決して順調な運転ではなかったのです。
さて9月11日の開通式の様子は函館新聞に詳しく掲載されています。
それによれば、朝7時に盛大な見送りを受けて出発した「比羅夫合」は札幌に8時40分に、幌内には11時50分に到着します。
参加者一行は幌内炭鉱の視察後、札幌まで戻り、札幌の豊平館での式典に参加しました。
その時の式次第と夜会(祝賀パーティー)招待状も残されています。
なお、開拓使煤田開採事務係がはじめたこの幌内鉄道の敷設は、明治15年(1882年)2月の開拓使廃止にともない「工部省田開採事務係」、「工部省岩内幌内両炭山並鉄道管理局」「工部省岩内幌内両炭山並鉄道煤田並鉄道管理局」さらに翌明治16年(1883年)の開通式のときには「農商務省北海道事業管理局」と管理部門が変わります。
幌内鉄道はこの後も名称、管理主体が次々とかわっていきます。
手宮線
現在は遊歩道として整備されています。(^_^)v
Warning: Undefined variable $add_ids in /home/takahashi-taxi/www/wp-content/themes/takahashi-taxi/recommend.php on line 57